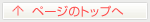ボクシング コラム
予備動作との戦い(2018-2-28)
パンチを打つ時に、私が一番注意を払っていることは、
出来る限り、相手に気付かれずにパンチを出すっていうことです。
極端な話、パンチを打つって判断した直後は、
ほぼ、そのことしか考えていないです。
いきなりズバッとパンチを当てることができない人は、
この感覚を養うことが大切だと思います。
もっともっと具体的に説明します。
相手に気付かれないようにするには、
今からパンチを出すって頭(脳)が決断した瞬間から、
パンチ(グローブ)が始動し始めるまでに、
体の他の部分、例えば、顔や膝や腰や肩は動いては
いけないっていうことです。
“動かしちゃいけない”っていう意識・感覚が非常に重要で、
この意識をシャドーしてる時やサンドバッグを
打ってる時も常に持ち続けることが大切なのですが、
これが、できるようでなかなかできないみたいです。
パンチを打つ時に、潜在的に、人は、次のように考えてると思います。
■強く打ちたい
■気持ちよく打ちたい
■楽に打ちたい
この潜在的な意識が、すべて、“動かしちゃいけない”っていう
意識を忘れさせてしまっているように思います。
強く打つために、一旦体を逆方向に捻ってしまったり、
気持ちよく打つために、拳を振りかぶってしまったり、
楽に打つために、膝を、よっこいしょって曲げてしまったり、
パンチ(グローブ)を始動する前に、いちいち、予備動作が
入ってしまってるんです。
しかも、この予備動作が意外と自分で自覚しているよりも、
客観的にみると、大げさで、ゆっくりであることが多いんです。
つづく・・・・
アマチュアとプロの大きな違い(2011-3-10)
オリンピックの舞台を頂点とするアマチュアボクシングは、いわゆる反則の規定がプロに比べて格段に厳しい。
特に次の2つの反則はプロではほとんど反則にならないのに、アマチュアではすぐに反則になる。
1.ローダッキング(頭を低く下げてダッキングすること)
2.インサイドドブロー(拳の手のひら側の面を当てること)
プロではダッキングをして相手のパンチをかいくぐるのは、正当なディフェンステクニックであり、
常套手段といっても過言ではないですが、アマチュアのトップクラスでこの技術を使う選手はほとんどいない。
なぜか?というと反則を取られるからに他ならない。
ダッキングがすべてダメということではないが、例えば相手の腰の高さまで頭を下げればほぼ100%反則、
下げる位置がそんなに低くなくても顔が下を向いていたり、距離が相手の顔面にすごく近い場合も
かなり高い確率で反則になる。選手にとってさらにやっかいなのは、審判によって
問題ないダッキングと反則になるダッキングの境目がまちまちなところです。
甘めの審判なら少々のダッキングは反則にならないが、厳しい審判はほとんどのダッキングを反則扱いするので、
それなら、はじめからダッキングはやらないほうが身のためっていう結論が合理的なのだと思う。
インサイドブローについても厳しい。これはフックを打つ場合によくある反則だが、拳をしっかり
手前(自分側)に巻きこんで、指の付け根と第二関節の間の面を当てないと反則になる。
特にロングフックを打つ場合が難しい。ロングフックはヒジの角度が開く。ヒジの角度が開きすぎると、
必然的に手のひら側が相手の顔に当たる率が高くなるので、要注意である。
また、反対に接近戦での小さなショートフックもかなりヒジの角度を狭くしないといけないので
適当に当てにいくとインサイドブローになってしまう。
いわゆる猫パンチ的な打ち方は、アマチュアでは百害あって一利なしということです。
因みに、オープンブローっていう反則もあって、これは拳をしっかり握っていないという
反則で、インサイドブローと同じ状況で反則を取る審判もいます。
正直なところ、私は未だにこの反則の意味がよく理解できていません。
アマチュアのあんな大きなグローブの中に入っている拳をしっかり握っていようが、いまいが
外からの見た目には何も変わりはないと思うんですが。。。
ここで、アマチュアの五輪金メダリストでプロ転向後も世界チャンピョンに君臨した
Parnell Whitaker のアマチュア時代とプロの試合を紹介します。
ディフェンススタイルがまったく違うことにすぐに気付くと思いますが、
その理由は、上記で説明したとおりです。
プロのスタイルのほうが華があるし、見ていても「凄い!」って私は感じます。
余談ですが、スウェーバックはアマチュアでもまったく反則にはなりません。
私は元々ダッキングじゃなくスウェーバックをよく使うので、
幸いダッキングで反則を取られた経験もありません。
みなさん、そういう意味でスウェーバックは重宝しますよ!(笑)
オリンピック決勝
ちっちゃいダッキングはしていますが、スウェーやステップバックが主体です。
プロでの様子
思いっきりダッキングしまくってます(笑)。芸術的ですね!
ディフェンスの美学 その2(2010-8-17)
ロナルド・ウィンキー・ライトと同様のガードスタイルの
世界チャンピョンレベルの選手は他にもまだいます。
■ジョシュア・クロッティ(元IBF世界ウェルター級王者)
動画
■フェリックス・シュトルム (WBA世界ミドル級王者)
動画
■アンドレアス・コテルニク(元WBAスーパーライト級王者)
動画
共通して言えるのは、
パーリング、ウィービング、ダッキングをほとんど使わないこと。
そして、皆、KO負けがほぼないのである。しかし、ブロッキング重視のディフェンススタイルなので
ダイナミックさや、華麗さはがまったくなく、素人には受けは良くないですね(涙)
また、欠点もあって、どうしてもこのスタイルでは連打を打つのが難しくなるので、
有効打よりも手数や積極性を重視するジャッジには分が悪いです。(プロの場合)
コテルニクはこのパターンでカーンとアレキサンダーに連敗しちゃいました。
私は常にガードを上げている訳ではないですが、時と場合によって、すぐにこの
ガードスタイルに切り替えるボクシングをします。上記の中ではクロッティのガードに近いと思います。
両腕で顔面を包み込むようにブロックするこのディフェンス、出来そうで上手くできないんですが、
使いこなせるようになってしまうと、かなり武器になりますし、体で避けるディフェンスに比べて、
スタミナをほとんど消耗しないので、スタミナの無い人や重量級の人にはお勧めです。
因みに、あのメイウェザーもアマチュア時代にはブロッキングを多用していました。
当ててなんぼのアマチュアの世界では特に有効だということでしょうね。
ディフェンス美学 その1(2010-6-1)
私自身のボクシングのスタイルはかなりディフェンス重視です。
攻撃も楽しいですが、相手のパンチをもらわないことにも攻撃と同じくらい快感を感じます(笑)。
例えると、10発当てて5発パンチをもらうより、5発当てて一発ももらわないようなボクシングをします。
こういうスタイルになったきっかけは、私のアゴの脆さに原因があるのですが、
「打たれ弱い」という意味ではなく、文字通りアゴの関節が脆いのです。
これはスパーリングをしてみて初めて気が付いたのですが、一発でもジャブをまともにもらったり、
軽いフックでもアゴに一発もらうだけで、アゴの関節が痛くなってしっかりと食べ物を噛むことができなくなるのです。
ボクシングを始めて数か月の頃、私よりキャリアのある相手に何発もパンチをもらい、1週間くらいアゴが痛くて
食事をするのが苦痛で苦痛でたまらなかったという経験をしました。自分のアゴの脆さに嫌気がさして、それ以来
自分がこのアゴで大好きなボクシングをやり続けるにはパンチをもらわない技術を極める以外に道は無いと思ったのです。
それからはYoutubeで色んなボクサーのディフェンスを研究する日々が始まりました。
今の私のスタイルのお手本となった選手は何人もいますが、一番のお手本は、間違いなく
ロナルド・ウィンキー・ライト(Ronald Winky Wright)という選手の鉄壁のガード技術ですね。
上手くブロッキングできない方は、一度、こちら(赤いトランクスがWright)を参考にしましょう!
続く。。。
プロボクシングの採点 (2010-3-1)
プロボクシングの採点はラウンド毎に10-9とか10-8とかっていう減点方式で点数を与え、すべてのラウンドの
点数を合計する。接戦であってもどちらかを優勢(10-9)にするという方式になっている。
私もテレビで試合を見ながら採点することがあるけれどどっちが優勢なのか判断に苦しむラウンドっていうのが結構ある。
そんなラウンドでも優劣をつける必要があるんだろうか?五分五分だと思ったラウンドは10-10にしてあげるのが
戦っている選手にとって一番公平やと思うんやけど。。また、優劣をどのように考えるのかも”明確”な基準がない。
例えば、クリーンヒットの軽いジャブ5発と、一瞬体がよろけるような強烈なフック1発やったらどっちが優勢なんやろう?
思いっきり大ぶりのフックを10回振り回して積極的に前に出てきた選手に対して、すべてのパンチをいとも
簡単に芸術的に避けた選手はどっちが優勢なん?やっぱりジャッジって難しいよなあ。
細かく基準を作ればいいんやろうけどなあ。
なお、アマチュアボクシングの採点はプロのそれとはまったく異なっているので興味がある方はお気軽に質問してください。
スタートラインジムルールっていうのも考えてみようかなと思っている今日この頃。。。
好きな練習 (2010-2-25)
ボクシングのお決まりの練習メニューといえば、
縄跳び、シャドー、サンドバッグ、ミット打ち、マスボクシング、スパーリング くらいでしょうか。
当然ですがスパーリングについては、ある程度の技術を習得した方限定の練習メニューですね。
スパーリング以外は、初心者の方から熟練者までどなたでも同じように練習してもらっています。
どの練習が好きかは人それぞれですが、女性の方はミット打ちが好きな人が多いですかね。男性の場合は、
サンドバッグを思いっきり叩くのが好きな人が多いです。私が断然・ダントツで好きなのはマスボクシングや
スパーリングです。つまり、より実践に近い練習がお気に入りです。
ボクシングのいいところは、どのメニューでも自分のエンジンの掛け具合で、軽めの運動としても楽しめるし
ハードに自分を追い込んで鍛えることもできるという点ですね。
また、スタートラインでは上記の定番メニューだけではく、ボクシングに有効なオリジナルのメニューを
どんどん試して行きたいと考えています。みなさん、お楽しみに!
距離 (2010-2-19)
ボクシングでは相手との間合いは、大まかに分けると3種類ほどある。
1つはジャブを突いて当たるか当たらないかというくらいの遠距離。
2つ目はステップインしなくてもフックが当たる中間距離。
3つ目は頭と頭、グローブとグローブがくっついているような状態の近距離。
3つとも満遍なくこなせるボクサーもいるし、遠距離が得意やけど近距離は苦手というボクサーもいる。
私はリーチが長いので基本的には遠距離で戦うんやけど、カウンターを狙うときはわざと相手を中間距離に呼び込む。
私が一番嫌なのは遠距離、中間距離をすっ飛ばして、ズバッと近距離に入ってくるタイプのボクサーかな。
近距離になると技術的な優劣より、手数や馬力の勝負になることが多いのでスタミナのない私にとっては、
不利な展開になるし、見てる側からもゴチャゴチャしたボクシングになって見栄えもよくない。
私が唯一負けた試合は、(減量の失敗もあったのですが)まさにそんな展開でした(涙)
近距離になる前にそれを避ける戦い方、近距離になってしまった場合にすぐに抜け出す技術を習得しないと!
シューズ選び (2010-2-15)
いわゆるボクシング用のシューズというものも市販されているけれど、もちろんそんなシューズをわざわざ
買い揃える必要はまったくない。私は4年以上ボクシングをやっているが専用のシューズは買ったことがない。
ただ、確かに専用シューズは見た目がボクサーっぽくなってかっこいいのは間違いないから、「まずは形から」っていう人は
専用シューズを履くのもいいと思うけど、ある程度ボクサーらしい動きができるようになってからのほうが
いろんな意味で無難なのではないでしょうかね。
ボクシングに適しているシューズの条件は次の3つくらいかな。
1. 底が比較的薄いこと。
すり足で細かくステップするので底が厚すぎると安定感がなくなる。またリング自体が柔らかくクッション性が
ある場合が多いので、シューズまでクッション性を高くすると地に足がついている感覚が薄くなるし、足首をねんざする
要因にもなるので、靴底があまり厚いのはやめたほうがいいと思います。
2. グリップ性が高いこと。
ボクシングはたくさん汗をかくので床に落ちた汗を踏むと、グリップ性の低いシューズではスリップしてしまって
危険である。私も試合中にすべっておもいっきりひっくりかえって恥ずかしい思いをしたことがあります(笑)。
必ず靴底をチェックして柔らかめでグリップがよさそうなものを選びましょう。
3. 軽量であること。
これは言うまでもないですね。軽いに越したことはありません。
おまけ.... 安いこと。 ※私にとっては重要な条件(笑)
ボクシングと縄跳び
ボクシングの練習と言えば縄跳びというイメージがあると思う。私もボクシングを始めて数か月は
練習メニューの1つとしてやっていたけど、今はまったくやっていない。なぜか?そもそも
縄跳びの動きとボクシングの動きにはまったく似ている部分がないと思いませんか?
これまで色んな人に「なぜ縄跳びをするのか?」という質問をしてきたけれど的を得た答えは
聞いたことがない。よくステップの練習になるって言う人がいるけど基本的にボクシングステップは
横方向であるのに対し、縄跳びは縦方向にジャンプするだけなのであまり意味があるとは思えない。
確かに一定のスタミナを付けるのにはいいと思うし、縄跳び自体が好きな人には良い練習だと思うけれど
かといってボクシングに特に有効な練習だとは考えていません。
でも、やりたい人は遠慮なくやってくださいね。縄跳びやってボクシングの上達が遅くなるというこは
絶対にありませんので(笑)。偉大な世界チャンピョンの中にも縄跳びをやっている人はたくさんいますので
教える側の責任
過去に所属していたジムで、トレーナーがある会員の方に「パンチを打つときに、”シュッ、シュッ”って声を吐くな!」
って厳しく指導している場面に遭遇した。続けて「パンチを出すときに声出したら相手に読まれるやろ!」という説明。
軽く聞き流してしまえば、なんかまっとうな理由に聞こえるけど、よく考えて欲しいと思う。
声はパンチを出す瞬間に同時に出るものなので、相手がその声を聞き取ってパンチを読むなんてことはできるわけがない。
確かにその会員さんは吐く声が大き目やねんけど、声を出すことは全然悪いことではない。
何か動作を起こす時に、息を吐くことが自然のことであるのは誰もが知っていると思う。息を吐く時に「シュッ」
って音がでるもの至極当然のことである。人に何かを教える時は、それが正しいことなのかを自問自答すべし。
自信があることは自信を持って伝えればいいし、そうでない場合はそれなりの伝え方をしないといけない。
と、私が人にボクシングを教える時はいつもこのように考えながらやってます。
だから、少しでも指導内容についてわからないことがあれば「なぜですか?」って聞いてください。
必ず理由を答えることができるようにしますので。
右構えがいい?左構えがいい?
相手に対して、左足・左手を前にするのが右構え、右足、右手を前にするのが左構え(サウスポー)。
初めてボクシングをする人はまずどっちの構えがいいのかって話になるんやけど、正解っていうのは無い。
一般的には右利きは右構え、左利きは左構えと言われているけれど、手が右利きでも足が左利きの人もいるし
手が左利きでも足が右利きの人もいるので一概にそうとも言いきれない。私の考えは構えてみてパンチが
打ちやすいかどうかより、前後左右にステップしてみてよりスムーズに動ける構えを選べばいいと思う。
ただし、どちらの構えでも違和感がなくどっちが良いのか迷った場合は、左構えにするべきですね。
理由は分かりますか?
そう、左構えの選手の割合が低いからです。右構え同士で対戦する確率が圧倒的に高いので右構えの人は
稀に左構えの人と対戦すると勝手が違っていつもの動きができなくなるんですよね~。
そういう意味で左構えは得をします。左構えはいつも右構えの人と練習する機会が多いですからね。
ご意見やご質問がありましたらお気軽に、メールしてください
電話でのご質問も大歓迎です!→ 080-4390-9282